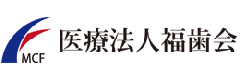医療法人 福歯会
ブログ
2013-06-08 15:19
顎関節症の主な病状とは?
かみ合わせの歪みが、痛みなどの病状を伴わないことも多いのに比べ、顎関節症は痛みなどさまざまな病状が現れるので、その発症を自分で自覚することができる。日本顎関節学会では、病状により、顎関節症を五つのタイプに分類している。
顎には左右の関節、顎を前に引っ張り出す外側翼突筋(そとがわよくとつきん)、こめかみの部分と下顎を結ぶ筋肉などからなる咀嚼筋があり、両方の顎の関節がバランスを取ることで前後左右に動くようになっている。これは他の関節にはない、特殊で複雑な動きだが、それを可能にするのが関節円板です。この関節円板は関節窩と下顎頭の間にあり、軟骨のような繊維質でできており、クッションの役目をするので、骨同士が直接擦れ合わないようになっています。これらの関節組織は、関節包という繊維質の膜に取り巻かれている。何らかの理由でこの関節円板がずれる(円板転位)と、顎の関節の障害や筋肉の障害を引き起こし、さまざまな病状が発生します。代表的な病状としては、顎が痛む、口が大きく開けられない(開口障害)、顎を動かすと音がする(関節雑音)、かみ合わせに違和感がある、口を完全に閉じることができない、などがあげられる。「顎が痛くなったがしばらくしたら治った」という比較的軽い病状から、重症になると手術が必要となったり、開口障害により食事の摂取が困難になるほど、日常生活に支障をきたすほどの病状に苦しむ人もいます。
顎には左右の関節、顎を前に引っ張り出す外側翼突筋(そとがわよくとつきん)、こめかみの部分と下顎を結ぶ筋肉などからなる咀嚼筋があり、両方の顎の関節がバランスを取ることで前後左右に動くようになっている。これは他の関節にはない、特殊で複雑な動きだが、それを可能にするのが関節円板です。この関節円板は関節窩と下顎頭の間にあり、軟骨のような繊維質でできており、クッションの役目をするので、骨同士が直接擦れ合わないようになっています。これらの関節組織は、関節包という繊維質の膜に取り巻かれている。何らかの理由でこの関節円板がずれる(円板転位)と、顎の関節の障害や筋肉の障害を引き起こし、さまざまな病状が発生します。代表的な病状としては、顎が痛む、口が大きく開けられない(開口障害)、顎を動かすと音がする(関節雑音)、かみ合わせに違和感がある、口を完全に閉じることができない、などがあげられる。「顎が痛くなったがしばらくしたら治った」という比較的軽い病状から、重症になると手術が必要となったり、開口障害により食事の摂取が困難になるほど、日常生活に支障をきたすほどの病状に苦しむ人もいます。
(C) 医療法人 福歯会