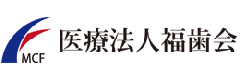医療法人 福歯会
ブログ
2015-08-22 15:58
歯なしにならないいい話
おいしいと感じれば噛む力はついてくる
硬い食べ物を上手に嚙めない子どもが増えていると言われています。
よく噛まない食事は十分な消化吸収を妨げるだけでなく、味覚の発達にも影響があるのをご存知ですか?
子どもに限らず、柔らかいものや甘いものを好むのは本能的な欲求で、同じ味で硬さの違う2つの食べ物があれば、ほとんどの動物が柔らかい方を好む傾向があるそうです。あごを動かして噛む運動にはエネルギーを使うので、噛まなくても楽に食べられる柔らかいものを好むのは当然。それでも人はなぜ噛むのか?といえば、直接的な動機は一つ。おいしさを味わいたいからなのです。
私たちは「食べ物を口にさえ入れれば自動的に味を感じる」と考えがちですが、味覚の仕組みはもう少し複雑です。舌や口の中の味蕾(みらい)という器官が味の刺激に反応し、味の情報が脳に伝わることではじめて「おいしい」と感じます。この一連の動きをより活発にするのが「噛む」という行為。柔らかいものばかりに慣れてしまうと、噛むことで味わえるおいしさを学ぶ機会がありません。
味の感じ方は食事の経験を重ねて変化し、拡大していくもの。噛むことの先にあるおいしさを知れば、噛む力は自然についてくるのです。
そのために重要なのは、硬いもの、柔らかい物を取り混ぜて、多種多様なおいしさを味わう食の経験を増やすこと。できる限り家族で食卓を囲み、楽しく会話しながら子どもの食事をよく観察することが一番です。また、子どもを一人きりで食事させる孤食は避けたいものです。楽しくない食事を早く済ませたいのは当然。味覚も広がらず、よく噛む習慣から子どもを遠ざけてしまう恐れがあるからです。
硬い食べ物を上手に嚙めない子どもが増えていると言われています。
よく噛まない食事は十分な消化吸収を妨げるだけでなく、味覚の発達にも影響があるのをご存知ですか?
子どもに限らず、柔らかいものや甘いものを好むのは本能的な欲求で、同じ味で硬さの違う2つの食べ物があれば、ほとんどの動物が柔らかい方を好む傾向があるそうです。あごを動かして噛む運動にはエネルギーを使うので、噛まなくても楽に食べられる柔らかいものを好むのは当然。それでも人はなぜ噛むのか?といえば、直接的な動機は一つ。おいしさを味わいたいからなのです。
私たちは「食べ物を口にさえ入れれば自動的に味を感じる」と考えがちですが、味覚の仕組みはもう少し複雑です。舌や口の中の味蕾(みらい)という器官が味の刺激に反応し、味の情報が脳に伝わることではじめて「おいしい」と感じます。この一連の動きをより活発にするのが「噛む」という行為。柔らかいものばかりに慣れてしまうと、噛むことで味わえるおいしさを学ぶ機会がありません。
味の感じ方は食事の経験を重ねて変化し、拡大していくもの。噛むことの先にあるおいしさを知れば、噛む力は自然についてくるのです。
そのために重要なのは、硬いもの、柔らかい物を取り混ぜて、多種多様なおいしさを味わう食の経験を増やすこと。できる限り家族で食卓を囲み、楽しく会話しながら子どもの食事をよく観察することが一番です。また、子どもを一人きりで食事させる孤食は避けたいものです。楽しくない食事を早く済ませたいのは当然。味覚も広がらず、よく噛む習慣から子どもを遠ざけてしまう恐れがあるからです。
(C) 医療法人 福歯会