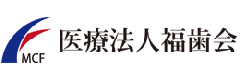医療法人 福歯会
ブログ
2016-07-21 15:45
味覚のしくみ
より味わい、より楽しめる
味覚のしくみ
食べるのが大好きな私たち。おいしいものを口に入れると瞬時に「おいしい!」と感じるように思いますがそこには、口と脳のすばらしい連携プレーが隠されています。歯科の見地から味覚研究に携わる脇坂聡先生に味覚のしくみや、より味わえる秘訣を伺いました。
意外とアバウトで、他の感覚に流されやすい味覚。
テレビのバラエティ番組で、目隠しをした回答者が、料理を一口食べて味だけで、それが何かを当てるゲームを観たことはありませんか?なかなか正解しないのを不思議に思ったことのある方もいるかもしれませんが、脇坂先生によると「実はそれくらい、人の味覚は”曖昧”なんです」とのこと。人が持つ五感(視覚、嗅覚、触覚、聴覚、味覚」の中で、他の感覚に一番影響されやすいのが、味覚だそうです。
「食べ物を味わう上で、影響力が強いのが”匂い”。風邪をひいて鼻がつまると、普段より味を感じませんよね。味覚を感じる器官は正常であっても、味を感じる感度はガクンと落ちてしまいます」。
先の番組のように、見た目の情報がなければ、私たちはなかなか味を判定できません。むし歯が痛むときは、それが気になって、食事を味わうどころではなくなります。なんとなく味を感じにくい味覚障害も、味覚の器官以外に原因があることが多いのです。
考えていたよりやや心許ない気がする味覚の正体。そもそも私たちは、どのように食べ物の味を感じているのでしょうか。
「よく味わうこと」には「よく噛む」ことが組み込まれている!
食べ物を味わうために、直接働いているのが舌や上あごにある「味蕾」という器官です。食べ物を口に入れて咀嚼することで、味の刺激を味蕾がキャッチ。その情報が脳へ伝わって、初めて「おいしい」と感知されます。
「食べ物を口に入れただけでは不十分。よく噛んで、唾液中に食べ物の成分を沁み込ませないと、味蕾は十分に味を受け取ることはできません。つまり、よく味わうためにはよく噛むことが欠かせないんですよ」。
味蕾の仕事を妨げる直接的な原因として、先生が着目するのが「舌の汚れ」。健康な舌の色は、薄いピンクかやや白みがかっている程度ですが、うっすら黄色っぽくなっていたら、舌表面に汚れがついている状態です。これは舌に溜まった、たんぱく質の汚れで、”舌苔”と呼ばれるもの。肌と同じように、舌や口の粘膜も新陳代謝しており、古い細胞が舌の表面を覆っていると、味蕾の先端まで味の成分が行き届きにくくなります。
「最近は、この舌苔も味覚障害の原因の一つとされるようになりました。毎回、歯みがきのときは、舌の色や感触に注意を向け、気になったら舌ブラシのケアを加えるのがおすすめ。舌の汚れを除去すれば、味覚感度が上がることが実験で証明されています」。
強く使いすぎると味蕾を傷つけることもあるので、まずは歯科医院で舌ケアの指導を受けるといいでしょう。最近は舌苔を分解する酵素を配合したタブレットも、市販されているので、それをときどき舐めるのも効果的です。
味覚のしくみ
食べるのが大好きな私たち。おいしいものを口に入れると瞬時に「おいしい!」と感じるように思いますがそこには、口と脳のすばらしい連携プレーが隠されています。歯科の見地から味覚研究に携わる脇坂聡先生に味覚のしくみや、より味わえる秘訣を伺いました。
意外とアバウトで、他の感覚に流されやすい味覚。
テレビのバラエティ番組で、目隠しをした回答者が、料理を一口食べて味だけで、それが何かを当てるゲームを観たことはありませんか?なかなか正解しないのを不思議に思ったことのある方もいるかもしれませんが、脇坂先生によると「実はそれくらい、人の味覚は”曖昧”なんです」とのこと。人が持つ五感(視覚、嗅覚、触覚、聴覚、味覚」の中で、他の感覚に一番影響されやすいのが、味覚だそうです。
「食べ物を味わう上で、影響力が強いのが”匂い”。風邪をひいて鼻がつまると、普段より味を感じませんよね。味覚を感じる器官は正常であっても、味を感じる感度はガクンと落ちてしまいます」。
先の番組のように、見た目の情報がなければ、私たちはなかなか味を判定できません。むし歯が痛むときは、それが気になって、食事を味わうどころではなくなります。なんとなく味を感じにくい味覚障害も、味覚の器官以外に原因があることが多いのです。
考えていたよりやや心許ない気がする味覚の正体。そもそも私たちは、どのように食べ物の味を感じているのでしょうか。
「よく味わうこと」には「よく噛む」ことが組み込まれている!
食べ物を味わうために、直接働いているのが舌や上あごにある「味蕾」という器官です。食べ物を口に入れて咀嚼することで、味の刺激を味蕾がキャッチ。その情報が脳へ伝わって、初めて「おいしい」と感知されます。
「食べ物を口に入れただけでは不十分。よく噛んで、唾液中に食べ物の成分を沁み込ませないと、味蕾は十分に味を受け取ることはできません。つまり、よく味わうためにはよく噛むことが欠かせないんですよ」。
味蕾の仕事を妨げる直接的な原因として、先生が着目するのが「舌の汚れ」。健康な舌の色は、薄いピンクかやや白みがかっている程度ですが、うっすら黄色っぽくなっていたら、舌表面に汚れがついている状態です。これは舌に溜まった、たんぱく質の汚れで、”舌苔”と呼ばれるもの。肌と同じように、舌や口の粘膜も新陳代謝しており、古い細胞が舌の表面を覆っていると、味蕾の先端まで味の成分が行き届きにくくなります。
「最近は、この舌苔も味覚障害の原因の一つとされるようになりました。毎回、歯みがきのときは、舌の色や感触に注意を向け、気になったら舌ブラシのケアを加えるのがおすすめ。舌の汚れを除去すれば、味覚感度が上がることが実験で証明されています」。
強く使いすぎると味蕾を傷つけることもあるので、まずは歯科医院で舌ケアの指導を受けるといいでしょう。最近は舌苔を分解する酵素を配合したタブレットも、市販されているので、それをときどき舐めるのも効果的です。
(C) 医療法人 福歯会