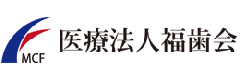医療法人 福歯会
ブログ
2016-08-12 15:59
味覚のしくみ
口の中だけでなく五感すべてを使って味は感知される。
私たちが感じる味覚の基本はかなりシンプルで、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の5種類。それらを組み合わせた無数のバリエーションによって、食べ物の味は構成されています。
「5つの基本味にはそれぞれ意味があり、これまでの人類の変化が関連しています。甘味(カロリー)やうま味(アミノ酸)は、多量でも受け入れやすい味。現代人はつい食べ過ぎてしまいますが、生きるために欠かせない栄養をしっかり蓄えようとする身体の仕組みなんですね」。
それほど味のメカニズムはよくできているのに、冒頭で述べた「味覚は曖昧なもの」というのはどういうことなのでしょうか。
食べ物のおいしそうな匂いが嗅覚を刺激すると強い食欲が湧いてくるように、人は五感すべてを総動員して食べ物を味わっています。歯ざわりや舌ざわりのほか、料理の見た目や周囲の音、食べる場所の居心地、食べ物にまつわる記憶、健康的に効果的といった情報など…。脳内では味覚以外の要素の方が大きなウエイトを占めているといっても、いいほどだそうです。
食の好き嫌いを決める要因も味覚の問題だけではありません。誰でも過去に食あたりを起こした食品は、どうしても好きになれないでしょう。逆に幼いころからなじみがあり何度も元気をもらった食べ物は、人生を通じて好物になるはず。親が苦手な食材はなかなか食卓に出ないため、子どもの「食わず嫌い」を招いて偏食の原因になることも。
味を感じることは決して舌や口の中だけの作用ではなく、五感を通じて脳が受け止める総合的な感覚。子どものころは嫌いだった食べ物が大人になると好きになることも多いように、味覚は”曖昧”だからこそ、さまざまな経験を敏感に反映しながら常に変化し続けているのです。
「子どものころからいろいろな味の刺激を与えて食の経験値を積み重ねることで、味覚の感度はどんどん発達していくんですね。多様な味を楽しめることは健康につながり、人生をより豊かに味わうことにもつながります」。
味覚の世界は自分の経験によって限りなく広がるもの。そう考えるとおいしものをしっかり味わうためのお口のケアもより楽しめる気がしませんか?
私たちが感じる味覚の基本はかなりシンプルで、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の5種類。それらを組み合わせた無数のバリエーションによって、食べ物の味は構成されています。
「5つの基本味にはそれぞれ意味があり、これまでの人類の変化が関連しています。甘味(カロリー)やうま味(アミノ酸)は、多量でも受け入れやすい味。現代人はつい食べ過ぎてしまいますが、生きるために欠かせない栄養をしっかり蓄えようとする身体の仕組みなんですね」。
それほど味のメカニズムはよくできているのに、冒頭で述べた「味覚は曖昧なもの」というのはどういうことなのでしょうか。
食べ物のおいしそうな匂いが嗅覚を刺激すると強い食欲が湧いてくるように、人は五感すべてを総動員して食べ物を味わっています。歯ざわりや舌ざわりのほか、料理の見た目や周囲の音、食べる場所の居心地、食べ物にまつわる記憶、健康的に効果的といった情報など…。脳内では味覚以外の要素の方が大きなウエイトを占めているといっても、いいほどだそうです。
食の好き嫌いを決める要因も味覚の問題だけではありません。誰でも過去に食あたりを起こした食品は、どうしても好きになれないでしょう。逆に幼いころからなじみがあり何度も元気をもらった食べ物は、人生を通じて好物になるはず。親が苦手な食材はなかなか食卓に出ないため、子どもの「食わず嫌い」を招いて偏食の原因になることも。
味を感じることは決して舌や口の中だけの作用ではなく、五感を通じて脳が受け止める総合的な感覚。子どものころは嫌いだった食べ物が大人になると好きになることも多いように、味覚は”曖昧”だからこそ、さまざまな経験を敏感に反映しながら常に変化し続けているのです。
「子どものころからいろいろな味の刺激を与えて食の経験値を積み重ねることで、味覚の感度はどんどん発達していくんですね。多様な味を楽しめることは健康につながり、人生をより豊かに味わうことにもつながります」。
味覚の世界は自分の経験によって限りなく広がるもの。そう考えるとおいしものをしっかり味わうためのお口のケアもより楽しめる気がしませんか?
(C) 医療法人 福歯会